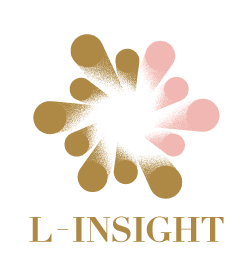セミナー「多様性と持続可能性: 責任ある研究評価と大学改革の課題」を開催しました(2024年10月8日)
L-INSIGHTと学術研究展開センター(KURA)は、10月8日、英国から来日中のJames Wilsdon教授を招き、セミナー「多様性と持続可能性: 責任ある研究評価と大学改革の課題」を共同開催しました。

本セミナーは、大学における研究評価やエビデンスに基づく分析の現状を振り返り、学術の発展に資する改革のあり方を探ることを目的として企画されました。会場の山内ホールには研究者のほか、評価等の実務者やURA、執行役員の先生方が80名近く参集し、活発な議論を行いました。司会はKURAの佐々木結URAが務めました。
第一部の冒頭、趣旨説明の中で、岩井一宏理事(企画・調整、評価、附属病院担当)・プロボストは、研究者が積極的に自己主張し、自ら研究環境を良くできるようなしくみをつくることへの思い、そして、そうした行為が研究を盛り上げていく時代へと変わることへの期待を述べました。
続くWilsdon教授による基調講演では、「責任ある指標の5原則」に基づいて、最近の欧州の研究評価の動向、とりわけ、人・文化に対する観点の導入について紹介がありました。これに対するコメントとして、北川進理事(研究推進担当)からは、創生を旨とする知の伝統における研究指標の適切なあり方について示唆が述べられました。
第二部ではパネルディスカッションを行いました。モデレーターの仲野安紗特定准教授は、冒頭で、ここでの議論の観点が、本学理事副学長や評価実務者との話し合いを通じて準備されたことを紹介しました。

登壇者の宋和慶盛助教(農学研究科)は、若手研究者がより高度な挑戦をしたくなるような報奨制度の存在は、より経験を積むための研究環境そのものである、と述べました。石川冬木副学長(研究支援担当)は、近代科学の導入の背景に触れ、将来的な影響を占い得ないという研究行為の価値について述べました。文部科学省からは科学技術学術政策局研究開発戦略課長の藤原志保氏が登壇し、評価と投資の連関について、個人としての考えを述べました。 こうした意見を受け、第一部の登壇者を中心として、会場から多くの意見が寄せられました。議論の継続の重要性を強調しつつ、セミナーは終了しました。
※本セミナーの報告書は作成中です。掲載が完了次第、このページでお知らせします。